1995年から3期12年にわたって倶知安町長を務めたのが、伊藤弘さん。それはひらふにとって、サンモリッツリフトの破綻からグラン・ヒラフの誕生、そしてオーストラリア・ブームと、世紀をまたいだ激動の時期でもありました。スキーへの思いと在任中の出来事などを語っていただきました。
 私は1942(昭和17)年室蘭生まれです。物心つくころからスキーが大好きでした。熱郛(黒松内町)から倶知安高校に汽車通学をしていましたが、ひらふにリフトができたのは高校3年のとき。1級下に、蘭越から乗ってくる気田義也君がいました。のちのオリンピック選手(インスブルック五輪、グルノーブル五輪に出場)です。そのころ私はまだ、くやしいけれど第2の壁をうまく滑ることができませんでした。もたもたしている自分の後ろからよく気田君が、呆れるくらいあざやかに滑り降りていったことを覚えています。後輩のくせになんて生意気なヤツだと、腹を立てたことがありました。(笑)。
私は1942(昭和17)年室蘭生まれです。物心つくころからスキーが大好きでした。熱郛(黒松内町)から倶知安高校に汽車通学をしていましたが、ひらふにリフトができたのは高校3年のとき。1級下に、蘭越から乗ってくる気田義也君がいました。のちのオリンピック選手(インスブルック五輪、グルノーブル五輪に出場)です。そのころ私はまだ、くやしいけれど第2の壁をうまく滑ることができませんでした。もたもたしている自分の後ろからよく気田君が、呆れるくらいあざやかに滑り降りていったことを覚えています。後輩のくせになんて生意気なヤツだと、腹を立てたことがありました。(笑)。
高校を出て大学の夜間に通いながら道庁に勤務し、主に水産畑を歩みました。もちろん大人になってもスキー熱は冷めません。水産経営課長だったとき、さまざまな縁から、倶知安町長選への出馬をすすめられました。倶知安町長になったら、道庁勤めよりもはるかにひらふでスキーができる。今だから言えますが、それが出馬の動機のひとつになりました(笑)。
就任すると役場にスキー部「チームじゃが太」を作って、そのころ普及しはじめていたインターネットで部の活動を発信したり、道内外のいろんな方と交流しました。スキー好きの町長として知られると、町のPRにもなりますからね。ゲレンデではいつも、倶知安町のキャラクターであるじゃが太が背中に入ったジャンパーを着て、ネット上のハンドルネームも、じゃが太。

どんなに仕事でストレスがたまっても、ゲレンデに来るとすっきり空っぽになれました。年間30回〜40回は滑っていました。土日、祝日、年末年始、とにかく仕事から解放される時間のほとんどはスキー。大晦日深夜、年明けのたいまつ滑走も楽しみでした。私のこの熱中ペースに職員の一部には次第に敬遠する人もいましたけれどね(笑)。
1997年11月に北海道拓殖銀行が破綻してしまいました。サンモリッツ社(アルペンリフト)のメインバンクは北洋銀行でしたが、拓銀の道内の営業が北洋銀行に譲渡されたことから、北洋銀は不良債権処理を一段と厳格化します。これが過剰な設備投資などで負債にあえぐサンモリッツ社の資産差し押さえ手続きに発展するという情報が私の耳にも届いていました。
その年のスキーシーズンの到来を間近に控えてサンモリッツ社のリフトが差し押さえられてしまう事は、町の屋台骨をも揺るがす一大事!と判断した私はすぐさま北洋銀行の本店(札幌)に乗り込んで、リフトの運営はなんとしても続けられるようにしてほしいと訴えました。
結局サンモリッツリフト社は北洋銀行のグループ会社である交洋不動産が経営することになり事なきを得ました。21世紀になってからは、最終的に、ニセコグラン・ヒラフとしてアルペンリフトと高原リフトをひとつの会社が運営するいまの形に落ち着き、たいへん良かったと思います。
21世紀の幕開けには「21世紀カウントダウンinひらふ」というイベントで盛り上がりましたね。私は実行委員長を務めました。
スキーを通していろんな出会いがあり、倶知安を知ってもらいました。ゲレンデでよくじゃが太さん!と声をかけられました。そういう方は私が町長であることなど知らないし興味もなく、ただスキーを愛する親父ということで仲間だと思ってもらっていたのです(笑)。ゲレンデを案内することはもちろん、アフタスキーのガイドもずいぶんしたものです(笑)。
オーストラリアの皆さんがやってくるようになると、国のビジットジャパン・キャンペーンの一環としてオーストラリアを訪問して、エージェントや観光関連企業にひらふの魅力を積極的に売り込みました。このころ、まちで海外からのゲストやツーリストに出会うとできるだけ声をかけ、「1日20回ウェルカム握手をしよう」と心がけていました。
例えば1000メートル台地でリフトを降りると、猛吹雪–。ときにはそんなことがあります。何も見えず、右も左もわからず、視界のすべてはただ真っ白。たまらずひとりうずくまって、自然の力をしみじみと思います。人間はなんて小さな存在なんだ、と。山と雪への畏敬の念が自然にわいてきますね。
これから倶知安町やひらふスキー場がどんな歴史を歩んでいくのか。どんな時代になっても、人間は自然に対するこうした畏敬の思いをなくしていけないと、私は強く思います。人生でスキーと出会うことができて、私は幸せ者です。
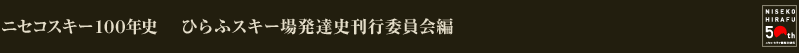




 1959(昭和34)年1月、その前に後志支庁長を務めていた高橋清吉さんが倶知安町長に初当選しました。新町長は企業誘致と観光振興を軸にした新たなまちづくりを掲げて、総務課に企画室という部署を作りました。初代の室長が、34歳だった私です。町長はトップセールスで、チシマザサを原料とする合板工場(北海道ファイバーボード)の誘致に動きましたが、私はそのお供をしました。一方で、岩内町も誘致をめざしていました。
1959(昭和34)年1月、その前に後志支庁長を務めていた高橋清吉さんが倶知安町長に初当選しました。新町長は企業誘致と観光振興を軸にした新たなまちづくりを掲げて、総務課に企画室という部署を作りました。初代の室長が、34歳だった私です。町長はトップセールスで、チシマザサを原料とする合板工場(北海道ファイバーボード)の誘致に動きましたが、私はそのお供をしました。一方で、岩内町も誘致をめざしていました。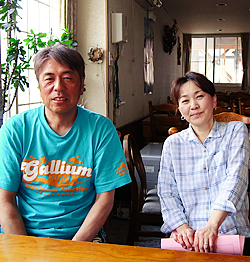
 倶知安スキー連盟は2001年から3年続けてJOCジュニアオリンピックカップをひらふに誘致して、倶知安は2年連続で総合優勝を飾りました。3年目の03年では男女大回転で大越龍之介、寺田さんの娘である雪華両選手が優勝。寺田選手は回転でも2位に入り、2年連続して最優秀ジュニアオリンピックカップを受賞しました。倶知安高校に進んだ雪華さんは、2005年の全国高校スキー大会のアルペン女子回転で2位となりました。
倶知安スキー連盟は2001年から3年続けてJOCジュニアオリンピックカップをひらふに誘致して、倶知安は2年連続で総合優勝を飾りました。3年目の03年では男女大回転で大越龍之介、寺田さんの娘である雪華両選手が優勝。寺田選手は回転でも2位に入り、2年連続して最優秀ジュニアオリンピックカップを受賞しました。倶知安高校に進んだ雪華さんは、2005年の全国高校スキー大会のアルペン女子回転で2位となりました。





