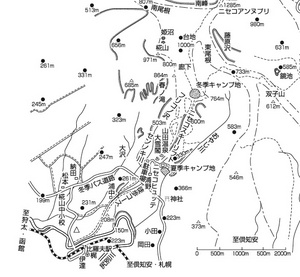新年を迎えるグラン・ヒラフの名物といえば、「大晦日たいまつ滑走」。35回目となる今年も、参加スキーヤーの募集がはじまっています。今回はこの「たいまつ滑走」のお話です。

ひらふの「たいまつ滑走」のスタートは、1975年。はじめたのは、現在グアム政府観光局日本代表の光森裕二(56)さんです。小樽生まれで札幌育ちの光森さんは、子どものころからスキーが大好き。高校生になってもその情熱は熱くなるばかりで、冬はニセコ高原ホテルのレストランで住み込みのアルバイトをしながら、スキー漬けの日々をおくっていました。
「バイト仲間もスキーに夢中になっているやつばかり。だから大晦日のカウントダウンのイベントに、なにかおもしろいことやろうぜ! という話になったのです。紅白歌合戦を見ているだけじゃつまらない、とね」
光森さんたち10数名はスキー場の理解を得て、スキーをかついて第一ゲレンデを第二の壁の上まで登り、午前0時を期していっせいに滑りはじめました。これぞ正真正銘の初滑り。これは面白い! それならばと次の年光森さんは、たいまつを持って滑ることを提案。角材に布を巻いて灯油をしみこませ、灯火とともに滑りました。
「ニセコ高原ホテルの人たちが手伝ってくれたのです。そんなこと危ないからやめろ、と言われるかもしれないと思っていたので、うれしかったですね。それからひらふの行く年来る年は、リフト(ホテル)の協力をいただきながら、このイベントが恒例となっていきました。今年でもう35年なんですね」
その後観光業界に進んで何度も海外勤務を経験した光森さんですが、海外にいるときでも年末には必ずひらふに帰って、仲間たちとたいまつ滑走の運営にあたってきました。
1980年代になって本州からのスキーツアーが盛んになると年末のリピーターの中から、自分もたいまつ滑走をしてみたい! と希望する人たちが増えて、滑走者は200人前後にふくらみました。ニセコひらふでたいまつ滑走をして年を越すことがステータスのようになって、その魅力が口コミで広まっていったのです。また当時は、一般客が気軽にたいまつ滑走に参加できるスキー場はほかにほとんどありませでした。21世紀を迎える2000年のミレニアムには280名を超えるスキーヤーが参加して、忘れられないビッグイベントとなりました。
光森さんは、世界のスキーリゾートの中でも、一般客がこれだけのスケールで楽しむたいまつ滑走はない、と言います。もともと若者たちのノリでスタートしたこのイベント。ボーゲンができれば誰でも参加でき、細かな決まりはありません。今ではオーストラリアや東アジアからのスキーヤーも欠かせない顔ぶれとなり、世界に開かれたスキー場にふさわしい光景となっています。
「私たちは、ただ好きだから、面白いからと、みんなでやってきました。その自由さが、たくさんのスキーヤーや運営ボランティアを引きつけているのではないでしょうか。それと自慢がもうひとつ。いままで吹雪で中止になったことは、一度もないんです! スキー場開設50周年に向けて、70年代にニセコヒラフでスキーを一生懸命していた人たちとまた会えれば、とてもうれしいです!」
今年も、たくさんの参加者と見物の皆さんが集うことを、大晦日のヒラフが、待っています。

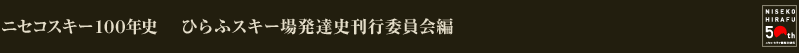 |
|
 |
 |



 旅館コロポックルの岡田光義さん、英子さんご夫妻 2010年9月撮影
旅館コロポックルの岡田光義さん、英子さんご夫妻 2010年9月撮影
 旅館銀嶺荘の岡田智信さん 2010年9月撮影
旅館銀嶺荘の岡田智信さん 2010年9月撮影
 元旅館さかえ 坂井正行さんご夫妻お孫さんとともに 2010年9月撮影
元旅館さかえ 坂井正行さんご夫妻お孫さんとともに 2010年9月撮影